こんにちは、ココロの雑学Lab.です。
今日は「良い人を演じるのをやめる勇気」について、私自身の経験も交えながらお話ししたいと思います。
「またみんなのために無理してる…」
「本当は行きたくないけど、断れなくて…」
「いつも自分の気持ちより、周りを優先してしまう…」
こんな思いをしたことはありませんか?
実は私も長年、「良い人症候群」に悩まされていました。
周りからの評価を気にするあまり、自分の気持ちを押し殺し、いつも笑顔で「大丈夫!」と答えるのが習慣になっていたんです。
でも、その結果どうなったか。
心は疲れ果て、人間関係はどこか空虚で、本当の自分がどこかに行ってしまったような…そんな虚無感に襲われていました。
この記事では、「良い人」を演じることをやめて、自分らしく生きるための具体的な7つのステップをご紹介します。
これは心理学の知見と私自身の経験から編み出した、実践的なアプローチです。
良い人症候群とは?自己犠牲の罠にハマっていませんか
良い人症候群とは、周囲からの評価や承認を得るために、自分の気持ちや欲求を無視して他者に尽くし続ける状態のことです。
日本では特に「和」を重んじる文化があるため、この症状に悩む人が多いんです。
良い人症候群のサイン・チェックリスト
以下のチェックリストで、あなたが「良い人症候群」かどうか確認してみましょう。
- □ 「NO」と言うのが苦手で、頼まれごとをつい引き受けてしまう
- □ 自分の本音よりも相手の期待に応えることを優先する
- □ 人から嫌われることに強い不安を感じる
- □ 自分の意見を言うとき、相手の反応を気にしすぎてしまう
- □ 周りの人の機嫌を取ることに疲れを感じている
- □ 「自分の気持ちがわからない」と感じることがある
- □ 我慢することが美徳だと思っている
3つ以上当てはまる場合、あなたは良い人症候群の傾向があるかもしれません。でも大丈夫、これは決して珍しいことではないんです。
良い人を演じ続けるとどうなる?
長期間「良い人」を演じ続けると、心と体にさまざまな影響が出てきます。
- 心の疲れがたまる:感情を押し殺し続けることでストレスが蓄積します
- 自己喪失感:本当の自分がわからなくなり、虚無感に襲われます
- 人間関係の質の低下:表面的で深みのない関係になりがちです
- 突然のキレや爆発:溜め込んだ感情が予期せぬ形で噴出することも
Aさん(32歳・会社員)の場合
「職場でも家庭でも常に笑顔で、断ることができなかった私。
気づいたら休日も仕事の連絡に対応し、友人の相談に乗り、自分の時間がゼロに。
ある日、些細なことで大泣きして動けなくなり、心療内科を受診しました。
医師からは『過剰適応』と診断されました。」
良い人をやめたら、人生はどう変わる?実体験から語る変化
私が「良い人」を卒業してから経験した変化をお伝えします。
1. 本当の自分を取り戻せる
自分の気持ちに正直になることで、「これが本当の私なんだ」という感覚を取り戻せます。
自分の好きなこと、嫌いなこと、大切にしたい価値観が明確になります。
2. 心のエネルギーが増える
無理をして我慢する必要がなくなると、心の余裕が生まれます。
「疲れた」と感じる頻度が減り、好きなことに使えるエネルギーが増えます。
3. 人間関係が深まる
驚くべきことに、自分の本音を出せるようになると、人間関係はむしろ良くなることが多いんです。
表面的な関係ではなく、お互いを理解し合える深い関係が築けます。
Bさん(28歳・看護師)の場合
「患者さんにもプライベートでも『いつも優しいね』と言われることが自分のアイデンティティになっていました。でも、自分らしさを取り戻す練習をしてから、本当に大切な人間関係だけが残り、かえって充実した毎日になっています。」
自分らしさを取り戻す7つのステップ
それでは、「良い人」から卒業するための具体的な7つのステップをご紹介します。
ステップ1:自分の感情と向き合う時間を作る
まずは自分の気持ちを知ることから始めましょう。
日記を書いたり、静かに瞑想したりする時間を作ります。「今、どんな気持ち?」と自分に問いかける習慣をつけるのがおすすめです。
実践ワーク
毎晩寝る前に5分だけ、今日感じた感情を箇条書きで書き出してみましょう。「嬉しかった」「イライラした」など、単語でOKです。
ステップ2:小さなNOから練習する
いきなり大きな場面でNOと言うのは難しいもの。まずは小さな場面から練習しましょう。
例えば、
- カフェでドリンクの希望を聞かれたとき、本当に飲みたいものを選ぶ
- 「この週末予定ある?」と聞かれたら、すぐに「大丈夫です!」と答えず、「確認して連絡します」と時間を取る
ステップ3:自分の境界線(バウンダリー)を設定する
自分を大切にするには「ここまではOK、ここからはNG」という境界線を設定することが大切です。
例えば、
- 仕事のLINEは19時以降は返信しない
- 自分の休日は月に最低2日は完全に自分のために使う
- 金銭の貸し借りは親しい友人でも○万円までにする
ステップ4:断り方のフレーズを用意しておく
断るのが苦手な人は、使えるフレーズをいくつか用意しておくと安心です。
柔らかい断り方の例
「その話、とても興味深いです。ただ、今は別の優先事項があって・・・」 「申し訳ないけど、今回は見送らせてもらえますか」 「ごめんね、その日は別の予定があって難しいんだ」
ステップ5:周囲の反応に振り回されない練習をする
人は他者からの評価に敏感ですが、それに振り回されない心の筋肉を鍛えることが大切です。
実践ワーク
あなたの決断や行動に対して、10人いれば10通りの反応があると想像してみてください。
そのうち、何人かはきっとあなたに否定的な反応をするでしょう。それは、あなたの価値が下がったということではなく、単に「意見が違う」だけなのです。
ステップ6:自己肯定感を高める習慣を取り入れる
自分を認めることができれば、他者からの評価に依存する必要がなくなります。
毎日の自己肯定ワーク
- 毎晩、今日うまくいったことを3つ書き出す
- 鏡を見て「あなたは十分素晴らしい」と自分に言ってみる
- 自分の強みリストを作り、定期的に見直す
ステップ7:同じ悩みを持つ仲間を見つける
一人で変わろうとするのは大変です。同じような悩みを持つ人と繋がることで、お互いに成長を応援できます。
オンラインコミュニティや読書会などを探してみるのもいいでしょう。
具体的に使える!相手を傷つけずに自分の意見を伝えるテクニック
「自分の気持ちを伝えたいけど、相手を傷つけたくない」
そんなジレンマを感じる方に、アサーティブコミュニケーションのテクニックをお伝えします。
「わたしメッセージ」を使う
「あなたは〜すべき」ではなく「わたしは〜と感じる」という形で伝えましょう。
NG例: 「いつも約束の時間に遅れるあなたは非常識だ!」
OK例: 「約束の時間に遅れると、私は大切にされていないような気持ちになります」
SETCモデルを活用する
- S(状況):具体的な状況を説明する
- E(感情):自分の感情を伝える
- T(考え):自分の考えを伝える
- C(希望):どうなってほしいかを伝える
使用例
「昨日の会議で私の意見を途中で遮られたとき(状況)、悲しく感じました(感情)。私も会議に貢献したいと思っています(考え)。次回は意見を最後まで聞いてもらえると嬉しいです(希望)」
まとめ:自分らしく生きるための最初の一歩
「良い人」を演じることをやめ、自分らしく生きるための7つのステップをご紹介しました。
- 自分の感情と向き合う時間を作る
- 小さなNOから練習する
- 自分の境界線(バウンダリー)を設定する
- 断り方のフレーズを用意しておく
- 周囲の反応に振り回されない練習をする
- 自己肯定感を高める習慣を取り入れる
- 同じ悩みを持つ仲間を見つける
人生は一度きり。他者の期待に応えるだけの人生ではなく、自分の気持ちに素直な、本当の自分らしい人生を歩んでいきましょう。
最初は不安かもしれませんが、小さな一歩から始めれば大丈夫。
あなたが本来の自分を取り戻し、もっと自由に、もっと自分らしく生きられることを心から応援しています。








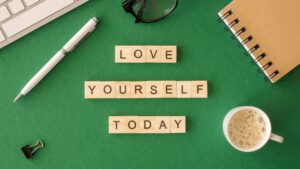
コメント